台風被害から始まった鋸南町のSOTOCHIKU
・・・・・・・・・・
みなさん、お元気ですか?GRIDFRAMEの田中です。
<台風被害から始まった鋸南町のSOTOCHIKIU>
2019年9月9日、房総半島台風から5年が経ちました。住宅被害がひどかった鋸南町は、建て直す費用を工面できず町外へ転出する人がいる状況が未だに続いているそうです。
GRIDFRAMEは、鋸南町の保田駅前で2022年1月から「パクチー銀行」というカフェ&SOTOCHIKUショールームを佐谷恭さんと共同経営しています。


台風が襲来したのは、佐谷さんが鋸南町でコワーキングスペースとアーティストレジデンスを始めるために別の物件を契約した直後でした。ズタズタの状況の中で事業を始めてよいか迷った末、「困っているときほど人の手は必要なはず」と復旧のためのボランティアとして関わることから始められました。
ぼくが佐谷さんにアプローチしたのは2020年11月です。SOTOCHIKUはまだ具体的なプロジェクトとして成立しておらず、ひたすらSOTOCHIKU素材を探していた頃のことです。ある日、スタッフが休日に鋸南町に近い金谷港へ釣りに行った後、「台風被害によって壊れた岸壁の鉄筋コンクリートが置いてあるのが魅力的だ」とスマホの写真を見せてくれたことに始まります。その写真の素材としての魅力に憑りつかれて、13年来の知人だった佐谷さんに「これはまだ金谷港にありますでしょうか?」と意味の通じるはずのないメッセージを送ってしまいました。


結局、その鉄筋コンクリートは業者へ解体を依頼済みとのことで素材として寄付を受けることができなかったのですが、この問合せをきっかけに佐谷さんを訪ねて鋸南町を案内していただきました。そこでいろいろとお話しする中で、壊れた住宅や空家の多いこの町がSOTOCHIKU素材の宝庫であることを二人で確認したのです。
それから話はとんとん拍子で進み、SOTOCHIKU&89 unLtd.(通称:パクチー銀行)が完成し、ぼくらにとって鋸南町はSOTOCHIKU素材採取の主要な拠点になりました。
台風被害から5年、ということで、二人の活動が東京新聞(2024年9月10日)で紹介されました。
「例えば鋸南の土壁が、都心のおしゃれな店の内装に使われる。『これも、これも鋸南の物だよ』となれば、住民が誇れるようになり、活気づくんじゃないか」(記事中の佐谷さんの言葉)
<奥能登の豪雨>



奥能登にとって、今年2度目の大災害となった9月21日の豪雨被害。ちょうどスタッフMさんがボランティアのために20日から能登入りしていました。能登入りは3月以来10回目になります。私は22日にMさんと共にマツリズム関連の方々と合流して「あばれ祭後夜祭」に出席する予定でした。
以下、Mさんの報告書から20日、21日の様子です。
・・・・・・・・・・
9/20に輪島入りしてありんこの家(※ボランティアの拠点NPO)に宿泊予定であったが、雨が強まってきてBさんに連絡を取ると、「現地は雨がひどく夜は危険なので明日一緒に行こう」となった。七尾まで来ていたが、氷見に戻って車中泊した。七尾や氷見では雨はひどくなかった。
翌朝輪島に向かうべく穴水から山中に入ると、2箇所ほど山崩れの土砂が道路に入り込んでいたが、通ることができたのでそのまま門前に向かった。門前に入る頃には、雨は土砂降りになり風も強まっていた。氷見から移動して門前に入った感じでは穴水までは雨も弱く奥能登の日本海側のみ豪雨のようであった。後日雨雲レーダー画像を確認すると、輪島から珠洲にかけて日本海側に停滞した前線上に線状降水帯が発生していた。
9/21は子ども食堂の炊き出しと医大生の医療展(健康相談)の手伝いの予定だったが、門前に着くとただならぬ雰囲気で戦慄した。ありんこの家に着くと代表の堀口さんは不在でBさんが連絡を取ると八ヶ川と山に挟まれた立地の介護施設「楓の家」に泥流が入り込んで、泥かきのための人手が必要と言うことで「楓の家」へ向かう。
介護施設が被災した場合職員は入所者の世話があるので、基本的に震災や水害の片付けは行えない。今回の水害はたまたま門前に来ていたボランティア5名ほどで対応したが、泥かきの後ルームクリーンをしていかなくてならないので、10~20人の人員で10日程度かかると言うことだった。暗くなるまで作業してありんこの家に泊まった。



・・・・・・・・・・
22日に予約していた飛行機は豪雨でキャンセルとなり、新幹線とローカル線で朝9時頃にはなんとか能登半島の入口辺りの高松駅まで辿り着き、Mさんに迎えに来ていただきました。Mさんは土砂崩れが道を塞ぐのを2度も迂回したそうです。これでぼくは4月以来5度目の能登入りです。しかし、現地は豪雨被害で混乱し、早速「後夜祭は中止」という連絡がありました。
午後、能登町でマツリズムメンバーと合流し、山深い柳田地区の孤立した仮設住宅へペットボトルとバッテリーの運搬を行いました。山崩れや川の氾濫はそこらじゅうで起こっていて道を寸断しています。今起こったばかりで情報はないから、行っては引き返して回り道の繰り返しです。輪島、珠洲、能登町で100ヶ所を超える孤立地区があったようです。Mさん曰く、「地震の被害を目の当たりにした時も言葉を失ったが、水害はそれ以上だと言って差し支えない状況だった。」
23日は現地の方々とお会いして、GRIDFRAMEとしての今後の能登での活動についてご相談させていただきました。
24日朝にぼくが帰京した後も、Mさんは門前の「楓の家」の泥かきクリーニング、金沢から輪島への資材運搬、珠洲の側溝の泥上げの作業に参加して、27日に帰京しました。
今回の豪雨被害では、被災者のみならず、現地の支援者の心も折れかかっているという声が聞かれましたが、一方で全国からのプロボランティアと呼ばれている人たちの初動も早く、その後も次々とボランティアが集まっているそうです。なんとも心強い動きです。
人が人を助けたい、と思う気持ちの不思議に想いを馳せます。
<奥能登で伝えたい二つのこと>
ぼくは、もし後夜祭が開かれていたら、祭でお世話になった宇出津の方々に、以下の二つのことをお伝えしたいと思っていました。
【1.地震で壊れたモノが遠く離れた場所で未来へ活かされたこと】
被災した宇出津でそのままでは失われてしまうモノをSOTOCHIKU素材として寄付していただいたおかげで、東京の空間づくりで未来に活かされたことをご報告したかったのです。
能登半島地震発生から9か月が過ぎ、ぼくたちGRIDFRAMEは「能登半島地震で壊れたモノを未来へ活かすプロジェクト」と名付けた通り、地震で壊れたモノのご寄付を受けて、それらを素材として新しい空間づくりに活かすプロジェクトを二つ、東京で成立させることができました。




どちらも大規模とは言えませんが、時間の記憶を引き継ぐことに物理的な量はあまり関係がないと考えています。能登の魂とでもいうべきものを伝えることが本質であり、もちろんそれは全ての人に無条件に伝わる類いのものでもありません。魂が誰かに伝わるとすれば、その人がひとり静かに魂の宿るモノに一対一で向き合ったときのみです。
東京で成立した二つの空間は、そこで立ち止まる人に能登の魂を伝える可能性を持っていると信じています。そして、これからも能登の魂を伝えていく空間をいろんな場所でつくり続けていきたいと思います。
【2.魂の宿る町であり続けるために地震で壊れたモノを復興の素材として活用すること】
これが今後、いち早くぼくたちが実現しなければならないことではないか、と思っています。
最初は、遠く離れた場所に実現していくことのみを考えていましたが、奥能登に何度も出入りをするようになって、今、奥能登で壊れたモノを引き継いでいくことの必要性を感じています。


ぼくは、あばれ祭に参加させていただいたことで、祭は魂の宿る場所でしか成立しない、ということを全身で理解しました。そして、魂の宿る場所を引き継いでいかねばならない、と。
東日本大震災において、古い建物が一掃されて宅地造成された、時間的な連続性が絶たれてしまった町では、人のつながりもまた失われた、と聞きます。それはつまり、古い建物に宿っていた魂が失われたことに他ならないのではないか、と思うのです。
ぼくは、壊れたモノたちは過去の長い時間を記憶しており、崩壊したが故に何か強いものを放っているのを感じます。被災しなければ多くを語らなかったモノたちが、崩壊することで雄弁に語り始めるのです。魂を引き継いでいくためには、壊れたモノを一掃するのではなく、積極的に引き継いでいく必要があると感じています。
ぼくは、Vol.9の最後に書いた内容をお伝えしたかったのです。
「小さなプロジェクトでいいんです。ぼくらに能登半島地震で壊れた空間を再生するチャレンジの機会をいただけないでしょうか?」
これをいち早く実現しなければならない、と書いたのは、壊れたモノが公費解体などで一掃されてしまえば、過去との連続性を保つ術が失われてしまうからです。ぼくらで大量に使用することはできませんが、ぼくらが実現することでそのニーズを感じて、行動される方が増えていくことに期待しています。
現在、奥能登でつくりたいものを東京で試作中です。次号は、それを公開するつもりです。
「能登半島地震で壊れたモノを未来へ活かすプロジェクト」は、壊れたモノが消失した時点で終わります。そのときまでに、壊れたモノをどのくらい未来へ活かせるのか?が勝負です。
<一対一で向き合うために>
ぼくは、一対一で向き合う、ということを空間づくりのみならず、全ての目標に置いています。
アフリカで知り合った友人の紹介で、京都府八幡市円福寺のお坊さんだった加藤義観(ぎかん)さんを後輩とともに訪ねたのは京都大学の院2回生の頃でした。「泊めるのは禁止されているけれど、こっそり泊ってってください」と泊めていただき、夜遅くまで話を聞かせてくださいました。
義観さんは30代半ばだったはずです。社会へ出る直前のぼくに多大な影響を与えてくださいました。
今でも印象に残っているのは、「本を読んで強い印象を受けたら、著者を直接訪ねて、それを信じてよいかを判断する」と仰ったこと。例えば、「著者が京大教授であれば、こっそり講義に紛れ込んで、その人を眺める。直接話さなくとも、その姿を見るだけでいい」と。
思えば、「一対一で向き合うとはどういうことか」ということを教えてくださったのだ、と今なら分かります。
その後もお互いに行き来をして、何度かお会いしました。ぼくがニューヨーク州へ留学していた頃、バッファローまで訪ねて来てくださったことがあります。
人が好きな方でした。
興味を感じたら、まったく物怖じをしない。作務衣姿のスキンヘッドだから、一目で僧侶と分かる格好で、どこでも入っていかれます。おもしろい建築の邸宅の敷地内へ入っていかれて、犬が吠えて中から人が出てきたときには、ぼくは肝を冷やしましたが、すぐに相手を笑顔にしてしまいます。
その後、何度か学生の友人を連れて伺うような縁をつくってくださいました。
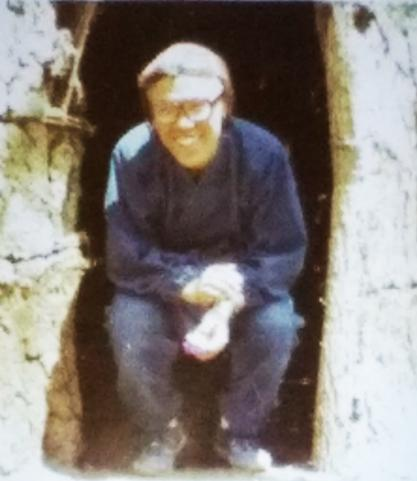

いろいろなお話を伺う中で「義観さんは結婚はされないのですか?」と訊いたことがあります。
義観さんはこう答えました。
「実は迷ったこともあるんだけど、お寺の檀家さんがなにか困りごとで相談に来られたときに、自分が孤独じゃなかったら、いつも喜んで相談に乗れないと思ってね。だから、結婚はしないことにしたのよ。」
やわらかい言葉に包まれた、重い覚悟。後になって気づくのは、ここで「一対一で向かい合うための条件」が語られていることです。
自分を疎の状態に保つ。この状態を基本として生きる。
加藤義観さんは、晩年に加藤月叟(げっそう)老大師と呼ばれ、2020年4月30日没。享年68歳。
義観さん、いつかまたどこかで。
<第3回ペンキのキセキ@鋸南パクチー銀行>

10月26日(土)10:30~16:00 約半年ぶりの開催になりました。みなさん、ぜひご参加ください!事前にご参加表明をお願いします。詳しくは下記のfacebookページまで。
https://www.facebook.com/events/1053619489371313
次号も、SOTOCHIKUの様々な活動について、お伝えしたいと思います。
2024 年 9 月 30 日 GRIDFRAME 田中稔郎


Comments are closed