奥能登の未来像
・・・・・・・・・・
みなさん、お元気ですか?GRIDFRAMEの田中です。
4月には、6日(土)に第2回ペンキのキセキ@鋸南町、17日(水)~19日(金)に奥能登の能登町へSOTOCHIKU素材の採取、という二つのイベントがあり、いくつかの制作プロジェクトでSOTOCHIKU素材を使用する準備も進んでいます。
第2回ペンキのキセキについては、vol6で詳しくご報告することにして、今回は奥能登でSOTOCHIKU素材の寄付を受けたことについて、ご報告します。
<能登半島活動報告>
4月17日(水)~19日(金)、「能登半島地震で壊れたモノを未来へ活かすプロジェクト」でGFスタッフMさんと共に奥能登を訪れました。
このプロジェクトは、能登半島地震で壊れた、時間を記憶したモノをSOTOCHIKU素材として寄付していただき、どこかの町でその記憶が受け継がれていくのを実現させることを目的とします。
4月6日(土)から12日(金)までの1週間、GFスタッフMさんが2度目の能登入りで、二つのボランティアに参加しました。
①前回の奥能登ベースキャンプで知り合ったピカリンさん主催の穴水町での「炊き出し」の手伝い


②能登町の倒壊した松波酒造から辛うじて助かった3500本の酒瓶を小松市の加越酒造本部でラベル貼り
②に参加したときに、松波酒造の若女将・金七聖子さんにSOTOCHIKUの話をしたところ、ご理解をいただき、18日(木)、能登町・松波酒造にて今回加越酒造本部で醸造したばかりの大吟醸「大江山GO」即売会の日に壊れたモノをSOTOCHIKU素材として寄付してくださることになりました。

日常を取り戻すために大変なときに、ご理解をいただいたことをとても感謝しています。
今回は、素材の採取と金七さんへのご挨拶のために、ぼくがMさんと一緒に伺うことにしました。
能登半島の付け根あたりまでは震災の影響を感じさせませんが、能登半島の先端へ向けて北上すると、だんだん道がつぎはぎに変わり、ブレーキを踏むことが多くなります。

能登半島の真ん中あたりにある七尾市に入ると、雨漏りを避けるためにブルーシートが貼られた家屋が目立ち始めます。8年前の、2016年4月に故郷で熊本地震が発生して1か月半後に帰省したときに見た、あのブルーシートの風景を思い出します。熊本空港の上空で高度が下がってくると、青い屋根ばかりの風景に胸が苦しくなったなぁ、と。母が一人で住む実家もやはりブルーシートが屋根に貼られていました。
でも、今回見た奥能登の風景はそのときの風景よりももっと胸を圧迫するものでした。
そこからさらに進んで、穴水町に入ると、重い瓦屋根の木造家屋は倒壊している状態のものが多くなり、もうブルーシートすら貼られていない家も多くなります。それは、もう人が住めないことを示しています。


今更ながら、ブルーシートの下には人の生活があったことを思い知りました。
・・・・・・・・・・
松波酒造のある能登町松波は、珠洲市との境にほど近い海沿いの地区です。数キロ北側と数キロ南側の地区は津波で大きな被害を受けました。
全国には30近い杜氏集団が存在し、その中でも岩手県の南部杜氏、新潟県の越後杜氏、兵庫県の但馬杜氏、そして石川県の能登杜氏が「日本四大杜氏」と言われているそうです。
松波酒造はその能登杜氏発祥の地、能登町で明治元年から続く歴史ある酒蔵。創業から150年以上たった今でも、昔ながらの道具を使いながら、厳しい能登の冬、手造りで極寒仕込みの酒造りをされてきました。


松波酒造も屋根にブルーシートはなく、ご家族は仮設住宅で生活されています。建物は震災当時のままで通常はだれも入らない場所ですが、この日は表側の安全なところにテントを張っての新酒即売会です。
道路に面する松波酒造の表側は、建物が傾いて庇が道路側へせり出す方向へ今も動いているそうで、いつ倒壊するかわからない状況です。

酒蔵の中も積み木のように、どれか一つでもずれると全体が崩れそうな様子でかろうじて立っているように見えます。


松波酒造の建物の裏側は、ほぼ倒壊した状態にあり、複雑にうねる瓦屋根が松波川の流れの中に崩れ落ちて、体を横たえる龍の背中のように曲線をなし、息遣いが聴こえてくるようです。


また、全てのカタチが崩れ落ちる中、酒米を蒸すための煙突だけがまっすぐに天を衝くように垂直を保っている様子が、歴史ある酒蔵の誇りを表現しているようで、その堂々たる姿に感動を禁じえません。
失われてゆくモノは、ときに雄弁に人へ語りかけることがあります。毎日、あたりまえのようにそこに在るときにはほとんど感受されることのない「かけがえのなさ」が心に染み入ってくるのを経験された方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

緑のホーロー製タンクにあった貯蔵酒と、酒米をレスキュー隊が救出できたことで、今回の新酒の販売が可能になりました。震災のショックを心に抱えながらも動き続けた金七聖子さんを始め、たくさんの方の魂が込められています。
やがて片付けられる壊れた酒蔵が語る時間の記憶をどこかの場所で受け継いでいくためには、酒蔵からほんの一部の素材を寄付していただき、その素材が使用されていた様子に思いを馳せながら、どのように使用するかを考えていこうと思います。
今にも崩れそうな建物の下でヘルメットを被り、しばらく佇んで150年に及ぶ酒造りの様子を想像して過ごしました。
今回、ご寄付いただいたモノたちは、次の通りになります。
・その新酒の入っていたタンクを支えていた角材

角材には酒の匂いが浸み込んでいました。貯蔵酒の救出時にかかったのかもしれません。
・そのタンクで作業をするための木製梯子階段

杜氏さんたちはこの梯子階段に上ってタンクの中を覗き込みながら、さまざまな細かい作業が行われたのだろうと想像します。
・100年以上前に焼かれた瓦

ぼくは震災前の奥能登を訪れたことがありませんが、奥能登の風景といえばきっと重い瓦屋根の木造家屋が立ち並ぶ姿だったのでしょう。今回の地震で、その大半は倒壊してしまった印象があります。この瓦は1枚1枚がふぞろいで温かみがあり、ぜひ後世へ残したいものです。今回、11枚を車で運びましたが、奥能登の道路がつぎはぎ状態だったため、激しい揺れで5枚が割れてしまいました。
・黄色が印象的な土壁の土

今まで土壁を寄付していただいた千葉県鋸南町や埼玉県上里町と比べると、能登の土は黄色味が強いのが印象的で、震災後3か月半雨に晒されたこともあって、土が粘土のようにやわらかくなっていました。そのため、壁としては切り出せず、土を採取させていただきました。
金七さんと寄付の契約を交わし、SOTOCHIKU素材を東京へ持ち帰り、現在は表参道のSOTOCHIKU ショールームに並べています。現在、制作中の現場へ持ち込んでの使用を検討中です。松波酒造さん、この度は本当にありがとうございます。
今後のご報告をお愉しみに。
<奥能登の未来像について~焦土/スクラップヤード/祭り>
松波酒造のある能登町松波を後にして、火災によって広大な焦土となった輪島朝市へ向かいました。

焦土と呼ばれる場所をこの目で見たことはぼくの生涯でたぶん一度もありません。テレビや映画ではたくさん見てきました。この写真をメールすると、妻から「ガザかと思った」と返事。正直な話、ぼくもそこに佇むと、胸が圧迫されて過呼吸になっているのを感じました。
でも、ひとことで言ってしまえば、混沌。
空間をつくる人間として、この風景を未来へ生かす方法はないか?
ぼくはその焦土を目の前にして、それに似ている混沌の風景について考えていました。

ぼくはかつて米国バッファローで建築の学生だった頃、スクラップヤードに夢中になったことがあります。そこへ建築模型の材料を探しに行っているうちに、そこを「誰が来てもおかしくない」空間だと感じ始めたのです。
捨てられた鉄スクラップは、ベンツだったりファミリーカーだったりした巷での価値を失い、1キロ数円の鉄の塊と見なされ、どれも機械によって叩かれたり、引きずられたりして、唯一無二の姿で野ざらしにされて重なり合っています。ぼくは建築の学生としてスクラップの山からプロジェクトに合うものを探すのです。

それは、建築の学生としては宝の山でした。しかし同時に、商品としてつくられたモノたちが自然に還った森のような場所でもありました。だから、探そうとする心から離れても、自分を開放することができる自由な場所なのです。
「誰が来てもおかしくない」場所と感じた理由はここにあるのだと思います。
では、この焦土をスクラップヤードに変換することができないか?
写真に撮れば、さらにはサラサラとスケッチすれば、焦土もスクラップヤードも変わりありません。つまり、物理的には何もすることはありません。混沌の行き過ぎを調整するために、写真のフレーミング効果を発揮するGRIDFRAMEでレイヤーをつくれば、愉しい場所へ変換できる可能性があると思います。
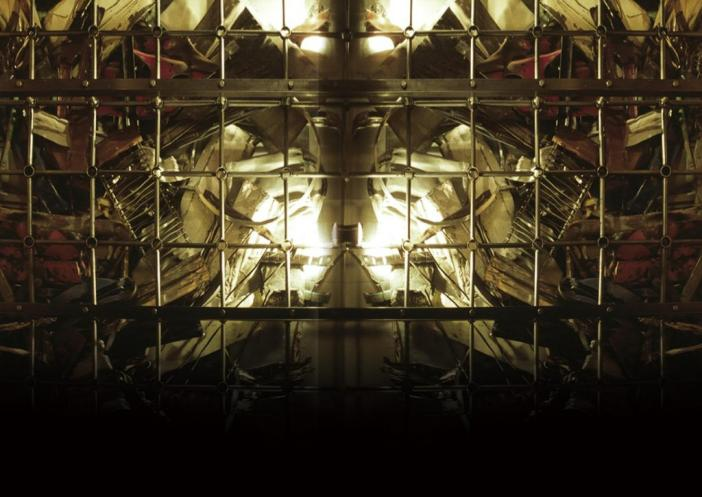
問題は、最初にぼくが感じた過呼吸になるような胸の圧迫の方です。これを取り払うためには、物語性を変換する必要があります。
SOTOCHIKU素材としては物語性を継承することを目標とし、現地の焦土の再生には物語性を変換することを目標としなければならない、という逆方向のベクトルが見えてきます。
そこで、もう一つ空間のモチーフとして考えたいのが、「祭り」です。これは、人々が望んで集まる「混沌」の空間です。これも物理的には問題なく変換が可能だと思います。元々、奥能登はキリコ祭りで有名だと聞きます。

キリコ祭りは、夏の約3ヶ月間、七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町の3市3町合計約200もの地区で行われる壮大な祭りで、キリコと呼ばれる巨大な御神灯が担ぎ出され、神輿のお供をしながら夜を徹して町を練り歩くそうです。その幕開けを飾るのが「宇出津(うしつ)のあばれ祭り」で、江戸時代、祭礼を行ったことで悪疫病者が救われたため、喜んだ地元の人がキリコを担いで、神社に詣でたのが起源とされているそうです。
このように、祭りはその発祥から地域が困難から立ち直ることに大きく関係しており、今回の能登の復興も、物理的にスクラップ&ビルドのカタチをとらないで経済的な消耗を抑えつつ、物語性を地鎮や鎮魂に変換することで、祭りによって人を集めていくことを一つの軸に定めてはどうでしょうか。
穴水市でボランティアを束ねる活動をされているピカリンさんから「能登の復興を遊び倒すくらいの勢いで日々を楽しみます」というメッセージをいただきました。復興を推し進めるのに必要なのは、この精神性以外にないだろう、と心から賛同します。
2024 年 4 月 30 日 GRIDFRAME 田中稔郎


Comments are closed